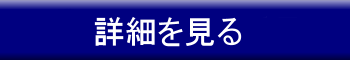【みんなのポイント資産】43億8968万8039円相当 (本日の増減 +2303円) [03:40現在]
■【茶器/茶道具 炉縁】 摺漆塗り 梅の木 前端雅峰作 国産梅材
サイズ外幅42.4m(1尺4寸)×高6.7cm(2寸2分) 内寸35.2cm 素材国産梅材 作者前端雅峰作 箱木箱 (限定・山丸江・298000)【初代 前端春斎】 生没年不詳 【2代 前端春斎(前端雅峰)】 1936年昭和11年 生まれ 初代 前端春斎長男 1948年昭和23年 県立山中漆器訓練所で越村計三、大下元作に蒔絵を学ぶ 1961年昭和36年 中村宗哲門下の塗師 村田道寛に茶道具 中村長寛に石地塗を習う 加賀蒔絵師 保谷美成に蒔絵を学ぶ 1973年昭和48年 村田道寛の推薦指導のもと 大徳寺瑞峰院本堂重要文化財解体修理の古材で棗を制作 瑞峰院吉田桂堂師より「雅峰」の雅号を受ける 大徳寺山門 金毛閣重要文化財解体修理の古材で棗を制作 1974年昭和49年 大徳寺芳春院 三重野与雲師依頼で石州好の棗を制作 1979年昭和54年 大徳寺管長方谷浩明大師の希望で 再び金毛閣古材で古厳松の棗を制作 1980年昭和55年 永源寺管長関雄峰老大師の依頼により永源寺古材で棗。香合を制作 1982年昭和57年 久田宗也好み展に出品 千澄子お好み展に出品 1983年昭和58年 大徳寺650年大遠忌記念に古材にて棗、香合を制作 中村祖順管長より「円如大虚」の昭和58年拝受 1984年昭和59年 裏千家坐忘斎若宗匠の格式披露茶会に松長板と建水を制作 1985年昭和60年 官休庵愈好斎33回忌法要に青海盆を製作 長男が3代 前端春斎を襲名 野村美術館にて個展 1988年昭和63年 古九谷と漆器の前端美術館開館 【3代 前端春斎】 1964年昭和39年 生まれ 前端雅峰長男 1982年昭和57年 植松抱民門下の保谷美成師に入門 1985年昭和60年 3代 前端春斎を襲名 ・・・・<参考資料>・・・・・ ●【伝承漆芸 系譜】 中村宗哲-中村長寛 -村田道寛-前端雅峰-前端春斉(秀樹) -土居義峰 -坂田峰俊 植松抱民-植松包美-吉田醇一郎 −結城 哲雄 −保谷 美成-前端春斉(秀樹) -坂田峰俊 【所属】 日本伝統工芸士会 日本工芸会石川支部 加賀美術協会 山中彩漆会
![[ポイ探] 【茶器/茶道具 炉縁】 摺漆塗り 梅の木 前端雅峰作 国産梅材](img/logo.20110121.png)